車いす利用者が日常で直面するバリアの一つが、スロープの勾配です。
自走するか押してもらうかや障害の程度にもよりますが、適切な勾配があることで、安全で快適な移動が可能になります。
私自身、床から車いすへのトランスファーが難しくなり、スロープの勾配が急だと、転倒しないかと恐怖を覚えるようになりました。
スロープの勾配とは?
スロープの勾配の定義と計算方法
「勾配(コウバイ)」というのはスロープの傾きのこと。
一般的には「何センチ上がるのに何センチ進むか」という比率で表します。
たとえば「1:12の勾配」というのは、「1センチの高さを上がるために12センチ進む」ことになります。
なぜ勾配が重要なのか?
スロープの勾配というのは、単に設計上の数字じゃなくて、使う人の安全や自立に直結するものです。
つまり、勾配が急すぎると、車いすで登るときに力が足りなくて登れなかったり、下るときにスピードが出すぎて危険だったりします。
逆に、ゆるやかすぎると設置スペースが長く必要になって、現実的に設置できない場所も出てきます。
なので、適切な勾配を理解して設計するのがとても大事です。
車椅子に適した勾配の基準
一般的に推奨される勾配
基本的に、日本では「1:12の勾配」がよく推奨されてるようです。
上にも書きましたが、これは高さ1センチにつき、長さ12センチのスロープが必要という意味です。
たとえば、段差が60センチなら、スロープの長さは7メートル20センチということになります。
これは「誰でも安全に使える最低限の基準」として設けられているものです。
でも実際には、それでもしんどいっていう人もいます。
だからよりゆるやかな「1:15」や「1:20」が理想的とされる場合もあります。
特に自走する人には「1:15以上」あるとかなり安心。
これは高さ1センチごとに15センチ進むから、より傾斜がなだらかになりますね。
ちなみに、公共施設やバリアフリー法のガイドラインでは「1:12以上」が基本です。
場合によっては「1:8」まで許されることもあるようですが、これは短いスロープとか、一時的な利用や介助者有りの場合を想定しています。
まとめると、「1:12は最低ライン。でも、使う人の負担を減らすには1:15〜1:20が理想的」という感じでしょうか。
他の国や日本の法規制について
この章は読み飛ばしてください。
アメリカでは、ADA(Americans with Disabilities Act)という法律があり、公共施設のバリアフリー化を義務付けています。
ADAによると、スロープの勾配は「1:12」以下でなければならないとされています。つまり、1インチの高さにつき、12インチ(約30センチ)の水平距離が必要ということなので、日本と同じですね。
ヨーロッパでは、EU(欧州連合)に「EUバリアフリー指令」というものがあって、公共施設や交通機関のバリアフリー化を進めています。
例えば、スロープの勾配については「1:12」や「1:15」など、国によって異なるけれども、利用者が安全に使えるようにするための基準が設けられています。
イギリスでは、1995年に制定された「Disability Discrimination Act(障害差別禁止法)」に基づいて、公共施設や建物のバリアフリー化が進められています。
スロープの勾配は通常「1:12」が推奨されていて、特に公共の建物ではこの基準が厳守されるようになっています。
アジアの国々では、例えばシンガポールがバリアフリーの取り組みが進んでいます。
シンガポールの「Building and Construction Authority(建設局)」では、公共施設や新築の建物に対してバリアフリー設計が義務付けられていて、スロープの勾配は「1:12」が一般的に求められています。
中国も近年、バリアフリー化を進めていて、新しい建物や公共施設には、利用者が安全に使えるようにスロープの設置が義務付けられています。
中国の基準では、勾配は「1:12」が一般的ですが、特定の条件下では「1:15」などの緩やかな勾配も採用されていることがあるようです。
日本ではバリアフリー法に基づいて、公共施設や新築の建物にはバリアフリー設計が求められています。
スロープの勾配については、一般的に「1:12」が推奨されているけど、場合によっては「1:15」や「1:20」といったより緩やかな勾配が理想的とされています。
実際の施設や駅のスロープ事例
具体的な施設や駅でのスロープの勾配例
公共施設や駅では、バリアフリー法に基づいて設置されていますので、「1:12」の勾配が標準とされています。
東京や新大阪など新幹線の駅や主要な都市の駅、、またショッピングモールや公共施設でも、同様の勾配が設定されています。
ここで勾配を【%】で表示する場会もあるのでまとめておきます。
勾配の表示
1:12 = 約8.33%
1:15 = 約6.67% (「1:12」よりなだらかな勾配になります)
スロープを利用する際の注意点
一般的に1:12や1:15の勾配なら、日常的に自走している車いすユーザーなら問題ないでしょう。
しかし、介助を常時必要とされている方や、自走に不安のある方は以下の点に気をつけてください。
急な勾配のスロープを利用する際のポイント
急な勾配の場合、安全を最優先に考えましょう。判断基準のポイントとしては…
- 体力の限界
余裕をもって上られない勾配なら、自走は止めておきましょう。
力尽きたり、手を滑らせたりすると思わね事故につながります。 - 車いすのコントロール
コントロールしにくいと感じたら、迷わずサポートを頼みましょう。
車いすの重心が後輪に近い場合、体力があっても転倒の恐れがあります。 - 周囲の確認
近くに通行人がいたりすると、思うように操作ができない場合があります。
介助者がいる場合のポイント
介助が必要な場合、通常は前向きに登り、後ろ向きに降りる方法が一般的です。
これは、前向きに登ることで安定した姿勢を保ちやすく、後ろ向きに降りることで急な下りでも制御しやすいためです。
体幹機能があまりない場合は、特に重要です。
安全第一に、無理をせず必要なサポートを受けるようにしてくださいね。
結論
スロープの勾配は、車いすユーザーの安全や快適な移動に大きな影響を与えます。
自分が設置する場合、適切な勾配を選ぶことは、使いやすさを大きく左右します。
一般的には「1:12」が推奨されていますが、より緩やかな「1:15」や「1:20」が理想的な場合もあります。
勾配が急すぎると、登るのが難しく、降りるときのスピードが危険になる可能性があり、逆に緩すぎると設置スペースが長くなりすぎて実現が難しくなります。
公共施設や駅では、法律に基づきバリアフリー設計が進んでおり、スロープは「1:12」の勾配が標準です。
しかし、ユーザーごとに必要な勾配は異なり、体力やサポートの有無に応じた適切な設計が求められます。
特に介助が必要な場合、前向きに登り後ろ向きに降りるなど、介助方法とも関係してきます。
車いすを使う方が快適に移動できるよう、スロープの設計はその人の状態に合わせた最適な勾配を考慮することが大切です。
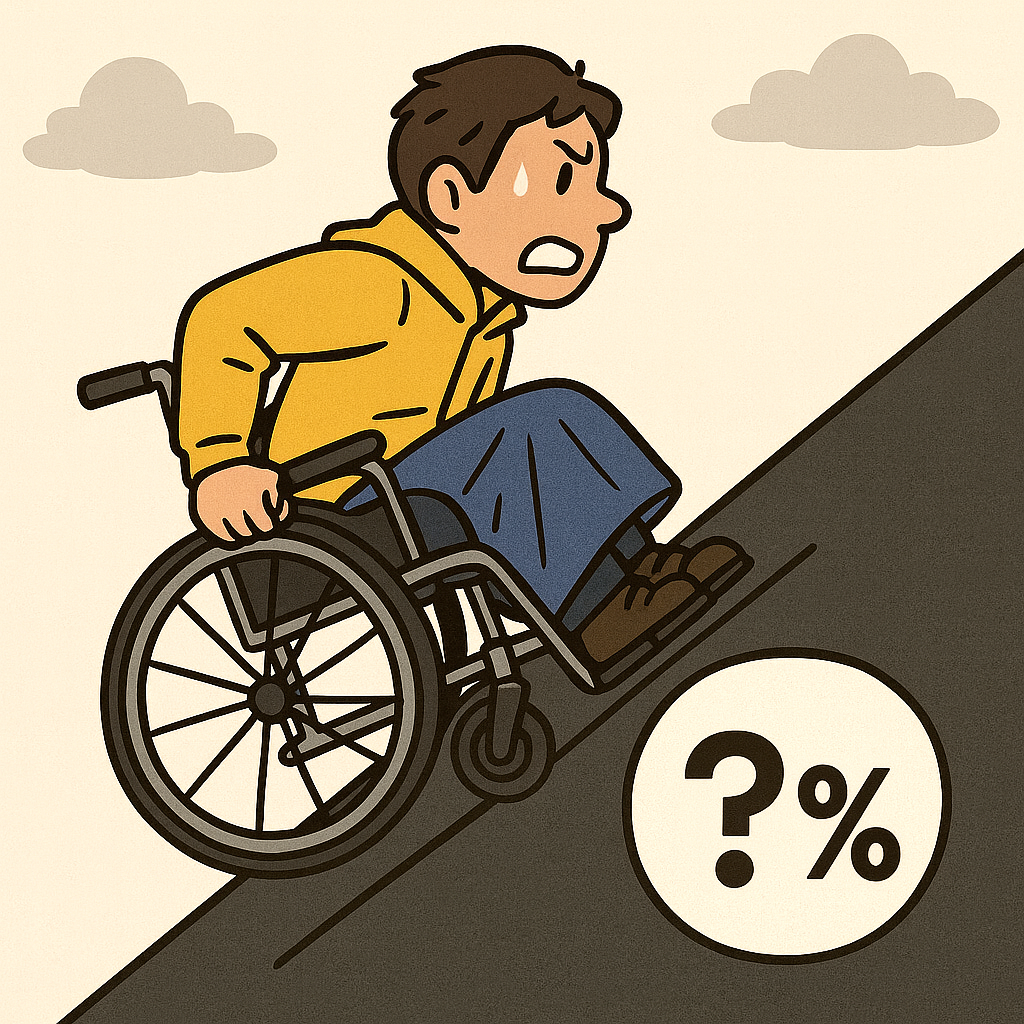

コメント