福祉車両には、補助金があります。
ですが実際には、
「補助金があると聞いていたのに、もらえなかった」
「あとから調べて、もう間に合わなかった」
という人が少なくありません。
原因は、制度が難しいからではありません。
買う前に知っておくべき“順番”を知らなかった、それだけです。
この記事では、
制度を細かく説明するのではなく、
「これを知らずに買うと失敗するポイント」
に絞って解説します。
※この記事は「福祉車両ガイド(全体マップ)」の一部です。
→ 福祉車両の全体像をまとめたハブページはこちら
そもそも福祉車両の補助金・助成金とは?
福祉車両の支援制度は、
全国共通で一本化しているものではありません。
大きく見ると、次のように分かれています。
・国の制度
・都道府県の制度
・市区町村の制度
この中で、
実際に補助金の可否を判断するのは市区町村
という場合がほとんどです。
そのため、
「当然貰えるものと思っていた」
「他の自治体では出たと聞いた」
という理由だけで判断すると、
思わぬ失敗につながります。
【最重要】補助金は「買う前」に決まる
ここが一番大切なポイントです。
福祉車両の補助金の可否は、
車を買ってしまうと、すでに手遅れです。
多くの自治体では、
・購入前の事前相談
・事前申請
・見積書の提出
といった手順が必要です。
この順番を飛ばしてしまうと、
条件を満たしていても補助金の対象外になります。
補助金は、
車の購入費用ではなく「改造費用の見積もり」に対して判断されるものです。
「ディーラーに任せれば大丈夫」は本当?
よくある誤解が、
「ディーラーに相談すれば補助金も大丈夫」という考え方です。
ディーラーは、
車を販売する専門家です。
一方で、
補助金の可否を判断するのは自治体です。
そのため、
「ディーラーが大丈夫と言った」
=
「補助金が出る」
とは限りません。
最終的な判断は、
必ず自治体の担当窓口が行います。
全国共通だと思うと失敗する理由
福祉車両の補助金は、
全国共通ルールではありません。
自治体ごとに、次のような点が異なります。
・対象となる障害の条件
・対象となる車両(新車・中古・改造内容)
・補助金の上限額
・申請できる回数
・申請窓口
「他の自治体では出た」という話は、
そのまま当てはまらないことが多いのが現実です。
自治体ごとの違いについては、
こちらの記事にまとめています。
👉福祉車両の補助金・減免制度【最新版】都道府県・市町村別ガイド一覧
中古の福祉車両でも補助金は出る?
中古の福祉車両についても、
よく質問を受けます。
答えは、
**「自治体による」**です。
・中古車でも対象になる自治体
・新車のみ対象の自治体
・改造費だけが対象になる自治体
など、対応はさまざまです。
「中古だから無理」と決めつけるのも、
「中古でも必ず出る」と期待するのも危険です。
中古車と補助金の関係については、2026年、筆者の実体験記事が始まります。
結局、補助金をもらえる人は何が違うのか
補助金をもらっている人が、
特別な知識を持っているわけではありません。
共通しているのは、次の行動です。
・買う前に自治体へ確認している
・申請のタイミングを守っている
・判断する窓口を間違えていない
知識ではなく、順番。
それだけの違いです。
自分の自治体について調べたい方へ
「自分の住んでいる地域はどうなのか?」
という方は、自治体別の記事をご覧ください。
👉福祉車両の補助金・減免制度【最新版】都道府県・市町村別ガイド一覧
まとめ|買う前に知っていれば防げる失敗
福祉車両の補助金は、
運や特別な条件で決まるものではありません。
・買う前に確認する
・正しい順番で動く
・判断先を間違えない
これだけで、防げる失敗がほとんどです。
関連記事(福祉車両コア)
- 福祉車両とは? 種類・特徴・選び方の完全ガイド【2025年版】
https://odekakejakusya.com/accessiblevehicle-core/
→ まず全体像(種類・選び方)を押さえたい方向けの入口ガイドです。 - 福祉車両の税金の優遇・減免ガイド(2025年版)
https://odekakejakusya.com/accessiblevehicle-core3/
→ 補助金と混同しやすい税制優遇を、別記事で分かりやすく整理しています。 - 自操用福祉車両ガイド|運転補助装置・改造・費用・支援制度を徹底解説(2025年版)
https://odekakejakusya.com/accessiblevehicle-core4/
→ 自操用の人は条件や選び方が変わるため、専用記事で詳しく解説しています。 - 福祉車両の買い方2025|新車・中古・改造の正しい手順
https://odekakejakusya.com/accessiblevehicle-core5/
→ 申請タイミングと噛み合う「購入の順番」をまとめて確認できます。
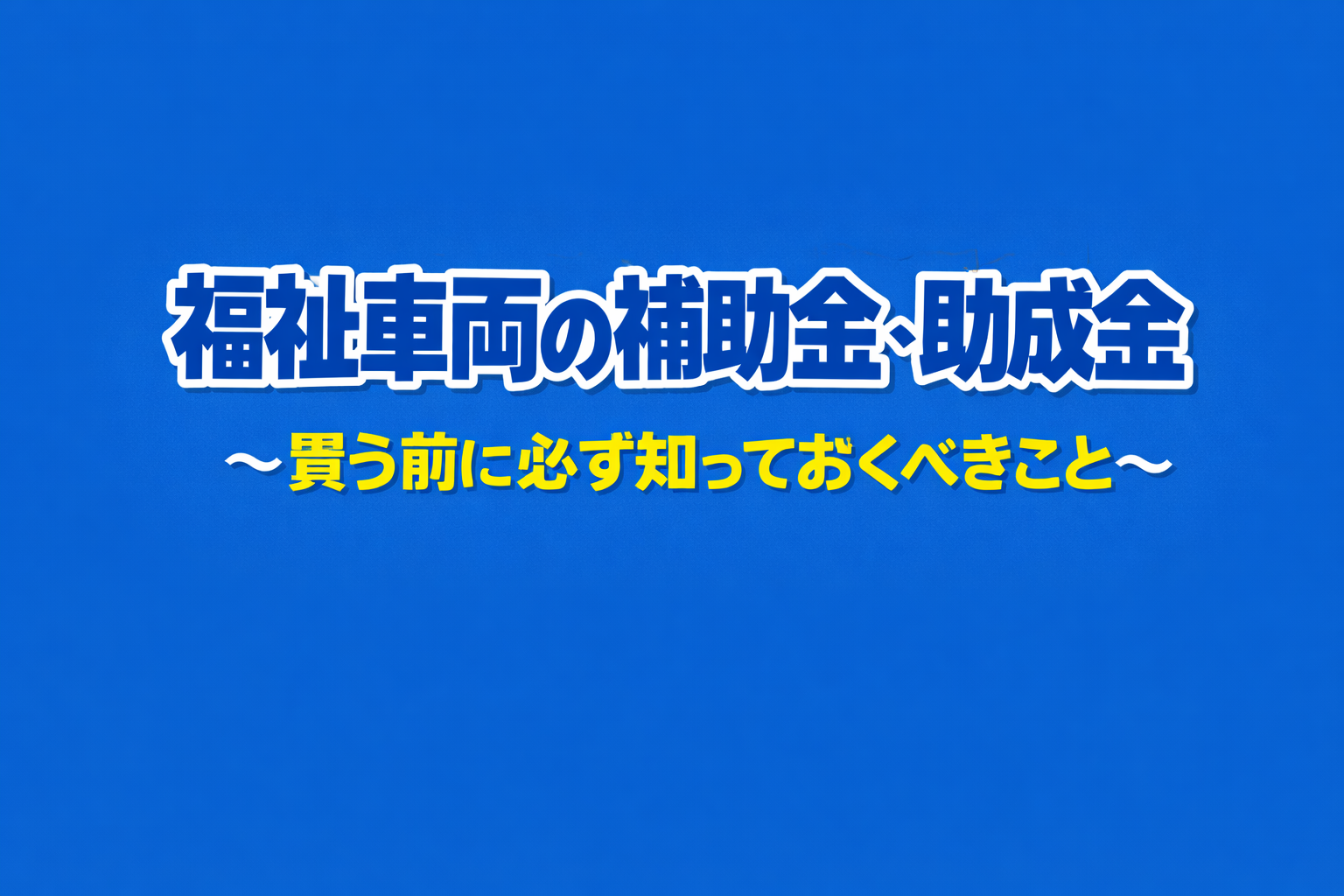

コメント